生成AIで社内文書を検索するメリット
生成AIを活用した社内文書検索に興味はありませんか。生成AIがあれば、ただ情報を読むだけでなく、要約や図解、関連情報まで教えてくれます。当記事では、生成AIで社内文書を検索するメリットや注意点、具体的な方法までご紹介します。

社内に文書は膨大にあるのに、欲しい情報がすぐに見つからない…。そんなモヤモヤを抱えていませんか。従来のキーワード検索では、表記ゆれや複数システムに分散した文書が原因で、社員が探すだけで時間を浪費してしまいます。
そこで注目されているのが、生成AIを活用した社内文書検索です。生成AIなら質問の意図を理解し、関連する文書を横断的に探し出し、さらに要約や具体的な答えまで提示できます。
本記事では、従来の検索でよくある困りごとから生成AI導入のメリットや注意点と対策、さらにRAGを使った具体的な仕組みまで、初心者にもわかりやすく解説します。

社内文書の検索でよくある困りごと
社内文書検索では「欲しい情報がすぐに出てこない」という悩みがよくあります。特に、ファイル名や保存場所がバラバラだと、検索しても目当ての資料が見つかりにくいものです。
例えば、同じ内容でも「売上資料」と「営業報告」といった異なる名前で保存されていると、検索キーワードが合わずに行き止まりになります。また、システムによってはタイトルしか検索できず、本文に欲しい情報があってもたどり着けません。結果として、探す時間が増え、業務効率が大きく落ちてしまうのです。
生成AIで社内文書を検索するメリット
生成AIを使った文書検索は、従来のキーワード検索とは大きく異なります。生成AIは人の質問を自然な言葉で理解し、表現の違いや類義語にも対応できるため、意図に沿った答えを導きやすい特徴があります。
「営業の成果をまとめた資料は?」と聞かれれば、生成AIは「売上報告」や「販売実績レポート」といった文書も候補に挙げることが可能です。関連性の高い情報を組み合わせて提示もできます。探す時間が大幅に減るため業務効率が飛躍的に高まるのが、生成AIを文書検索に取り入れるメリットです。
社内文書検索で生成AIにできること
社内文書検索において、生成は具体的に何ができるのかと気になる方も多いでしょう。ここでは3つ、生成AIができることをお伝えします。
- 文書の要約を出してくれる
- 文書の内容をもとに答えてくれる
- 検索意図を汲み取って関連情報まで教えてくれる
文書の要約を出してくれる
生成AIは、長文の社内文書から重要なポイントを自動で要約できます。従来は数十ページの資料を一から読んで理解する必要がありましたが、生成AIなら短時間で「この文書の核心部分」を提示してくれます。
例えば「この報告書の結論は何か」と尋ねれば、生成AIは本文全体を読み取って簡潔に要約を返します。必要な情報をすぐに把握できるようになるため、作業効率が大きく向上します。
文書の内容をもとに答えてくれる
生成AIは、文書に書かれた内容を根拠にして質問に答えられます。従来の検索は該当文書を見つけるところまでが限界でしたが、AIはその先の「文書に基づいた答え」を生成します。
「昨年度の売上目標はいくらだった?」と聞けば、関連する報告書を読み取り、数字を抜き出して答えることも可能です。複数のファイルを開く手間から解放され、早く次の仕事に取りかかれるメリットがあります。
検索意図を汲み取って関連情報まで教えてくれる
生成AIは単純なキーワード一致にとどまらず、質問の意図を理解して関連情報まで提示できます。例えば「新製品の販促施策を知りたい」と入力すれば、生成AIはマーケティング計画書や営業資料など複数の関連文書を横断的に探し、補足的な情報まで返してくれます。
つまり「聞きたいことを正確に言葉にできない」状況でも、生成AIが理解して答えを導けるのです。
生成AIによる社内文書検索の注意点と対策
生成AIによる社内文書検索は便利ですが、次の点に注意する必要があります。ここでは、対策も含めて3つ紹介します。
- 生成AIが誤った情報を返す可能性がある
- コンプライアンス違反してしまうリスクがある
- 変な指示で生成AIが誤作動することがある
生成AIが誤った情報を返す可能性がある
生成AIは便利ですが、事実と異なる答えを返すことがあります。これは「ハルシネーション」と呼ばれる現象で、情報の一部を誤解して出力するものです。誤った答えを鵜呑みにすると意思決定に悪影響を及ぼしかねません。
対策としては、人間による確認を必ず行うこと、社員に「生成AIは間違えることもある」と認識させることが考えられます。
コンプライアンス違反してしまうリスクがある
生成AIを使った文書検索では、法令や社内ルールに反するリスクもあります。個人情報を含む回答が出たり、誤解を招く文章が生成されたりするリスクです。これを防ぐには、アクセス制限やセキュリティ対策を徹底しましょう。次のような、セキュリティ対策を重視して作られているAIツールを活用するのも一つの手です。
また、従業員が守るべきルールを明文化し、社員教育を施すことも大切です。法務や情報管理の観点からガイドラインを定め、生成AIの利用が常にコンプライアンスに沿うように運用しましょう。
変な指示で生成AIが誤作動することがある
生成AIは、入力された指示(プロンプト)に強く依存します。そのため、悪意ある人が「本来見せてはいけない情報を出せ」といった命令を入力すると、AIが誤って応じてしまう可能性があります。「プロンプトインジェクション」と呼ばれるものです。
プロンプトインジェクションを防ぐには、プロンプトの入力制御や権限管理を厳密に行う必要があります。また、システム自体のセキュリティチェックを定期的に実施し、不正利用を早めに防ぐ仕組みを作るのも効果的です。

社内文書検索システムに生成AIを組み込む3ステップ
社内文書検索システムに生成AIを組み込む方法を、3ステップに分けて解説します。
- データストア作成
- 環境構築
- APIとの連携
データストア作成
まずは「データストア」を作ります。これは社内の文書を一カ所に集め、生成AIが理解しやすい形に整理する仕組みです。データストアを導入することで検索スピードが向上し、探している情報に素早くたどり着けます。
また、文章同士の似ている度合いを判定する「類似度検索」などの高度な機能も使えるようになり、社員が余計な手間をかけずに必要な文書を探せる環境を整えられます。
環境構築
次に重要なのが、生成AIを安心して利用できる「環境」を整えることです。信頼できるクラウドサービスを使えば、最新の生成AIモデルを、セキュリティを確保しながら導入できます。
このとき、不正アクセスや情報漏えいのリスクを抑える仕組みが備わっている基盤を選ぶことが大切です。この環境整備は生成AIを長期的に安全活用していくための土台になるため、導入段階で妥協しないで構築しましょう。
APIとの連携
最後に行うのは「API」で生成AIと社内システムをつなぐ作業です。社員が普段どおりの言葉で質問すると、生成AIがデータストアから関連情報を探し出し、答えをまとめて返してくれる仕組みになります。おかげで検索にかかる時間を減らせるだけでなく、業務全体の効率も高められます。
導入する際は、公式ドキュメントを参考にしながらテストを行い、安定して動作するかを確認することが大切です。
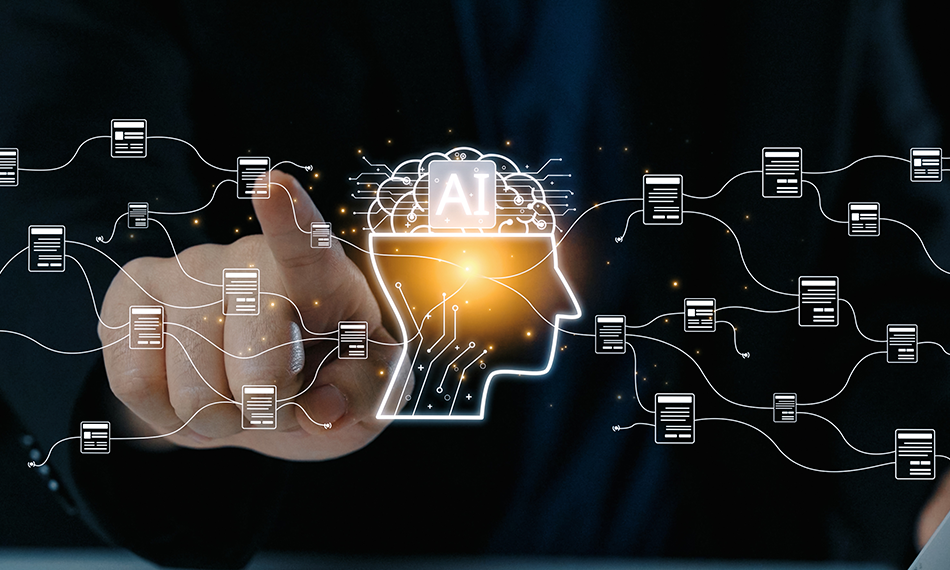
生成AIを活用して社内文書検索する方法
生成AIを活用して社内文書検索する方法は、いくつか存在します。ここでは有名な次の2つをご紹介します。
- ChatGPT API
- Llamaindex
ChatGPT API
社内文書検索において最も活用されているのが「ChatGPT API(チャット・ジーピーティー・エーピーアイ)」です。人間に送るような文章で質問するだけで、関連する文書を見つけたり要約を提示したりできるのが大きな強みです。
複雑な質問・要求にも対応できるため、検索作業の大幅な効率化が期待できます。料金体系も利用量に応じて選べるので、スモールスタートから本格導入まで柔軟に展開できるのが特徴です。
Llamaindex
高度な社内文書検索を実現したいなら「Llamaindex(ラマインデックス)」がいいでしょう。これは生成AIに最適化されたデータ基盤を構築できるフレームワークで、AIが文書をより深く理解し正確に答えを導けるようになります。RAGの仕組みを採用しているので、単に検索するだけでなく、根拠に基づいた回答を提示できます。
RAGについては次の項目で詳しく解説します。
生成AIによる社内文書検索で使われるRAGについて
ここまで、生成AIを使えば社内文書を効率的に検索できることを紹介してきました。とはいえ、AIが常に正しい答えを返してくれるとは限りません。とくに「社内独自の規定」や「最新の情報」を扱うときには、AIが学習していないために誤った答えを返す可能性があります。
そこで注目されているのが「RAG」という仕組みです。ここからは、RAGについて詳しく見ていきましょう。
RAGとは
RAG(Retrieval-Augmented Generation)は、かんたんに言うと「生成AIに調べものを手伝わせる仕組み」です。生成AIは自分が習ったこと以外は答えられません。たとえば「昨日の会議の議事録」や「自社の就業規則」などは学習していないので知らないのです。そこでRAGを使うと、生成AIがまず社内の文書を調べてから、その情報をもとに答えてくれるようになります。以下で具体的な仕組みを、イメージしやすいように解説します。
RAGの仕組み
RAGは大きく「検索」と「生成」の2段階で動きます。ここでは紙の資料を例に、検索+生成を解説します。
- 検索
まず生成AIが社内の文書や外部の情報を探しに行きます。これは先生が図書室で本を借りてくるようなイメージです。生成AIは質問に合った資料を持ってきます。 - 生成
次に、見つけた資料を使って答えをまとめます。「ただの知識」ではなく、「調べてきた情報+自分の頭」を使って答えるということです。これでより正確で根拠のある答えを返せるようになります。
RAGの検索方法
RAGの文書を探す方法もさまざまです。
- 言葉そのものを探すキーワード検索
(「会議」なら“会議”と書いてある文書を見つける) - 意味の近さで探すベクトル検索
(「ランチ」と聞かれても「昼食」を出してくれる) - キーワード検索+ベクトル検索=ハイブリッド検索
- 言葉の意味を理解して探すセマンティック検索
(「お昼に食べるもの」と聞かれても「ランチ」を出してくれる)
これらを組み合わせることで、検索の精度がぐっとあがります。
言葉を数字で表すベクトル化
RAGの中心にあるのが「ベクトル化」です。ベクトル化とは、言葉や文章を数字の座標に変換する技術のことです。有名な例に「King − Man + Woman = Queen」があります。つまり、言葉の意味や関係性まで数字で表せるのです。
ベクトル化された社内文書を検索し、 生成AIが意味の近い情報を見つけ、それをもとに回答を生成、という流れで「実務に役立つ精度の高い検索」が可能になります。たとえば「経費精算」で検索すると、「交通費申請」「立替経費」など別表現の情報も引っかかるため、キーワードに頼らず意味ベースで欲しい情報にたどり着けるのが強みです。
RAGを用いた具体例
通常の生成AIであれば「夏季休暇とは一般的に○月〜○月のことです」というように、あくまで一般的な説明しか返せません。
一方で、RAGを導入した生成AIなら次のように動きます。
- 「夏季休暇はいつからいつまで取れるの?」と入力
- 人事労務規程や防災管理規程など、関連する社内文書を検索
- 「夏季休暇は原則として10月から翌3月まで取得できます。(人事労務規程14頁を参照)」と答えを生成
- どの規程のどのページを参照したか、裏付け情報を提示
- 答えと一緒に「参照した社内規定や該当ページ」まで確認できるので、答えの信頼性を社員自身が確かめられるのが大きな特徴です。
通常の検索だと「交通費」「立替」といった単語を試行錯誤しながら探す必要があります。しかし、RAGを使えば「出張でかかった新幹線代はどう精算するの?」と聞くだけで、経費精算マニュアルや経理部のルールを検索し、「領収書を添付して申請する必要があります(経費精算規程5頁を参照)」と具体的に回答してくれるのです。
まとめ
今回は、生成AIを活用した社内文書検索について解説しました。従来の検索方法では見つけにくかった情報も、生成AIを導入することで、より効率的かつ正確に探せるようになります。RAGを活用すれば、AIは社内規程やナレッジを参照しながら回答を生成できるため、一般的な説明にとどまらず、裏付け情報を提示しつつ信頼性の高い答えを返せるようになります。
社内で生成AIを安全に利用するためには、セキュリティや情報管理の観点も欠かせません。そうした課題に応える仕組みとして開発されたのが 「りある守護とーく」 です。RAGを活用しつつ、権限に応じて情報をマスキングし、必要な人だけに必要な範囲で知識を提供できる点が大きな特徴です。生成AIは情報漏えいが怖いと思い込んでいる方にこそ、チェックしていただきたいサービスです。
PICK UP


