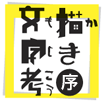
平野● 勉強のレベルが違うんだよ。ぼくは“原寸主義”“現場主義”。
小宮山■ 原寸でつくるのはどうもいいみたい。拡大縮小すると、どこか違ってきますね。とくに活字書体は原寸が基本でした。原寸でやると、どんな調整が必要なのか、すぐにわかるみたいです。
いまぼくが実際に描いているのは5センチ角ですから、本文にするとおおよそ15分の1くらいになる。原寸で彫った活字と違って、拡大原稿を描く際は、縮小されたときの姿を想像しろとよくいわれますが、ついつい忘れてしまう。やはり、縮小されたときに必要な調整というのは。拡大原字ではわかりにくいものですから、原寸の感覚を維持するのは非常に重要だと思いますね。
平野● ずっと拡大して描いていてね、プリントアウトしてみて、あっと驚いたりしてね。点が一個足りないんだ(笑)。
そもそも描き文字が登場した時代は、原寸しかあり得なくて、しかも活字や写植が対応できないサイズに対応することで重宝がられた面がある。つまり、描き文字は“原寸”で描かざるを得ない現場のなかで育ってきたんだよ。
川畑▲ 平野さんがおっしゃるように“原寸主義”“現場主義”は、戦前から脈々と受け継がれてきたデザイン文化の一端だと思います。
『日本レタリング史』(岩崎美術社、1993年)の著者でもあるデザイナーの谷峯蔵(1913〜)さんが、1930年代半ばの実務体験について語った一文を紹介しておきます。神田でデザイン事務所「レイアウト社」(1934年設立)を自営されていた頃の話で、当時のごく一般的な“街の図案家”の実態といったところでしょうか。
平野● ぼくが仕事をはじめた1960年代には、描けないことが恥だという風潮はもうなかったね。むしろそういう筆を持っていることを隠していた。描くことを隠そうという時代に入っていた。ぼくの場合は例外で、学校を出てデパートの宣伝部に就職したんだけど、催場の看板をみんなきれいな文字で描いてあって、すごくあこがれたんだ。だけどそれもすぐに置き換わっちゃった。置き換わるとみっともないことが起きるもので、いま地下鉄の出入り口あたりに貼ってある案内用の貼紙はみんなデジタル・フォントになっているじゃない、きっと駅員さんがキーボード叩いてやってると思うんだけども。みっともないよね。ちゃんと筆で描いたらどうだと思うことが多くなりましたね、ちょっとした逆転現象で。