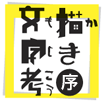
一方、サンセリフ体「ギル・サン」(1928〜30年)のデザインで有名なエリック・ギル(1882〜1940)の『エッセイ・オン・タイポグラフィ An Essay on Typography』は、1931年、わずか500部しか発行されなかった。原弘の旧蔵本は、交流のあった瀧口修造から「むしろあなたにふさわしい本」として贈られた一冊。ギルが同書で選択した紙は、淡いグレー色の二面耳付きのレイド紙。ザラっとした肌触りで、繊維はコットンラグ100%にドーサ塗布したもの。伝統的な洋紙製造法をほぼ踏襲した紙で、こちらも活版印刷に適した高級印刷用紙だが、印圧をおさえた刷りに適している。
タイポグラフィ史のうえでは新古典主義に分類され、いわば温故知新を実践したイギリスのモリソンやギルとは対照的に、機械美学を賛美したドイツのパウル・レンナー(1878〜1956)とヤン・チヒョルト(1902〜1974)は、より現代性を重視した紙選びを実践している。
サンセリフ体「フトゥーラ」(1927〜30年)のデザインで有名なレンナーの『機械化されたグラフィーク Mechanisierte Grafik』は、その副題「文字・活字・写真・映画・色彩」が示すように、タイポグラフィと同時代の機械美学の連関について論じた理論書。1930年刊。レンナーが選択した紙は、淡い茶褐色の平滑な紙。上記2種の中間の肌触りで、エスパルト60%と針葉樹晒サルファイトパルプ40%に、多量の澱粉と松脂サイズを加えているのが特徴。イギリスの両印刷紙に比べると、より現代的な製造方法が導入されているが、高級印刷用紙としてはやや劣る。
ドイツ書籍印刷教育連盟出版部から1928年に刊行されたチヒョルトの著書『ディ・ノイエ・テュポグラフィ Die Neue Typographie』は、革新的なタイポグラフィ論をまとめた理論書。チヒョルトが選んだ紙は前記三者とはまったく異なる乳白色のコート紙で、繊維は針葉樹晒サルファイトパルプ50%と機械パルプ50%で、白土をニカワで塗布してある。基本的に現在のコート紙と同じ製法を用いたもので、写真版の印刷に適している。この選択はチヒョルトが同書で重要視している写真とタイポグラフィの関係を重視した結果であろう。これはレンナーの『機械化されたグラフィーク』が、参考写真を巻末の口絵にまとめたのと対照的に、本文頁に数多くの参考写真を挿入するための選択と推察される。
資料提供・協力=特種製紙株式会社。
☆註7…1930年代半ばになるとアート紙が普及するが、上質紙を想定した従来の活字では画線が太くなるため、細いウエイトの本文用、とくに9ポイントの明朝体が必要とされた。そのため太く彫ってある活字を細く彫り直す「サライ」(あるいは「サラエ」)が流行した。この技法は岩田母型の種字彫り師・馬場政吉の創案といわれているが不詳(大日本スクリーン「タイポグラフィの世界 書体編」第7回「無名無冠の種字彫り師」参照)。大日本印刷が先鞭をつけたという説もあるが、築地活版の種字彫り師・安藤末松の述懐では晃文堂という。安藤末松は太く彫ってある9ポイントを細く彫り直して6000字ほどの細形9ポイントを揃えたが、あまり売れないうちに築地活版がつぶれたと回想している。築地活版の細形9ポイントの使用例には、『日本印刷需要家年鑑』昭和11年版(印刷出版研究所、1936年)などがある。
☆註8…インキだまりの処理は、写植書体特有の処理方法で、線が交差する部分に発生しやすい形状の乱れ・太まりを防ぐために、交差部に切り込みを入れる方法で、写植書体「本蘭明朝L」「岩田明朝 ILMA」(株式会社写研)などに顕著。小さなサイズで用いる場合は問題ないが、見出しなどの大きなサイズで用いる場合は、切れ込み部が際立つため、修正を要する。
平野● デジタル環境がつくりだした、なんでもござれみたいな状況を、道徳みたいな規範でとどめようとした。それで、ここ10年で一気にそういう傾向が強まったということか。
小宮山■ なにもないところに“規範”をつくろうとすれば、そうならざるを得なかったんじゃないかな。
川畑▲ 組版についてはそういう側面が強いと思いますが、別の一面もあると思います。
昨年、三島の特種製紙 Pam で「紙と印刷とデザインの実験室」[☆註6]という展覧会を企画したんです。
同社が所蔵する原弘さんの旧蔵本のなかからデザインやタイポグラフィに関する名著を選んで、その本文用紙の繊維分析をやってもらいました。この製紙会社には繊維分析のスペシャリストがいらしてデータも蓄積されていたので、それが可能だったんです。展示内容を一部紹介すると、スタンリー・モリソンの『過去と現在の活字デザイン』(1926年)、エリック・ギルの『エッセイ・オン・タイポグラフィ』(1931年)、パウル・レンナーの『機械化されたグラフィーク』(1930年)、ヤン・チヒョルトの『ディ・ノイエ・テュポグラフィ』(1928年)といったものです。
企画段階での基本的な問題意識としては、彼らにとってのフィニッシュとはなんだろうと考えたんですね。決して金属の塊をつくることが最終目的ではなくて、紙の上に押された文字の姿が重要だったはずだ……そう考えると、彼らは自身のタイポグラフィ論を著わす際に、自らがデザインした活字書体や選択した活字書体を、どんな紙に刷るかという用紙の選択も視野にいれていたはずだと想定したんです。実際、先に挙げた4冊では四者四様の結果がでましたね。しかもその紙選びが、それぞれのタイポグラフィ観とみごとに同調していて、たいへん驚かされました。
なぜこんな実験的な展示を試みたかというと、現行のデジタル・フォントはどっちつかずだなという批判めいた思いがあったからなんです。フォント自体が、どこまで印刷適性を意識して制作されているか、もしかしたらウェブなどのディスプレイ表示を重視しているのではないか、とね。現在、書体開発の現場では大半の作業がディスプレイ上で行われていますが、そこで産まれたものが、あらゆるサイズで適切に印刷できるかという検証はほとんど行われていないじゃないかな。別途プリンター・フォントが用意されていた頃はともかく、現行の OpenType では完全に表示と印刷の境界がなくなりましたからね。
平野● ずいぶんきびしい指摘だね。
川畑▲ そうかなあ。ボクが捉えてきたタイポグラフィの問題っていうのは、書体や組版だけの問題じゃなくて、用紙やインキなどの印刷環境、出版界や読者層の意識、それによって巻き起った社会現象など、もっと大きな枠組みのなかで共鳴しあっていたと思うんです。それが徐々に近視眼的な議論に終止しだしたという印象なんですけど。
小宮山■ 組版にデザイナーが関われるようになったのはかなり最近のことで、それまでは印刷関係者だけですよね。
川畑▲ 本文組みは出版社固有の顔、いわばトレードマークみたいなものという認識が強くて、デザイナーの個性を拒絶するというか、デザイナーになんか絶対に触れさせないという時代がながく続きましたから。
小宮山■ 印刷適性についていえば、金属活字は彫りますから、試印してすぐ直せる、フィードバックできる。印刷適性についてもっとも考えていたのは、もしかすると金属活字の時代かもしれない。1935年前後に、活字の画線を細くする「細形(細型)改刻」[☆註7]が流行したのは、明らかにアート紙への印刷適性を意識したからでしょう。
写植の場合はどうかというと、やはり印画紙上で終わっている。デジタルの場合もディスプレイ上で終わっていて試し刷りまでいかない。書体を開発する際に、実際に印刷された状態まで考慮しているかといわれれば、あまり考慮されてないかもしれない。
川畑▲ 写植の場合は、インキだまり[☆註8]を避けるためのくいこみがありますよね。
小宮山■ あれも初期のもので、実際は印刷技術が高まってくれば無用になります。
